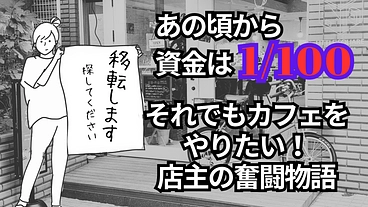支援総額
目標金額 3,000,000円
- 支援者
- 93人
- 募集終了日
- 2015年3月11日
僕が何者か(2)-葛藤。もしくは、一人だけを助けるということ
僕がこの一節を書いたのは、インドのデリーという場所に滞在していた頃です。そう、いま、10年に一度の寒波が吹きすさび、路上で暮らすホームレスに多くの凍死者が出たことだろう、と思い浮かべながら、僕は、ホームレスに手を差し伸べず、この文章を書き上げることに時間を費やすことにしました。
「社会的投資」という仕事は、酷な判断を迫られる仕事でもあります。人からお金をお預かりする以上は、約束事に基づいて、行動の指針を定める必要があります。もし、我々の支援者が”インパクト”や”持続可能性”を求めるのであれば、我々はそれを冷徹に追求していく必要があります。
社会の仕組みを変えるか、一人だけを助けるか。
さて、このような話は、インドに限った話ではなく、日本にいま、起きようとしている話でもあります。僕はインドを訪れる直前に、日本最大のスラムと呼ばれる「釜ヶ崎」を訪れました。
多くのホームレスが集い、朝からアルミ缶を探し、昼から酒を飲み、汚い格好で暮らし、夜が更けると、体温を維持するために、またアルミ缶を探しに出かけるという暮らしをしています。彼らの「職業」は時給に換算すると、せいぜい100円程度。良くて、200円に達するかどうかという暮らしをする。これからの日本を考えると、路上で暮らし、凍死する、という現実は、経済が衰退する中で増加傾向を辿らざるを得ないでしょう。
ところで、僕が生まれ育った場所から釜ヶ崎はそこまで遠くない場所にあり。こういう場所に当時あった活力が僕は好きだったりします。むしろ、そういう暗い何かの中に潜む衝動があったから、生きてこれたのかもしれない、とさえ思ったり。
途上国で物乞いにどう関わるか?ということと、社会への向き合い方
さて、発展途上国で語られるエピソードの一つで、五体不満足の物乞いや、もしくは、物乞いの子どもたちにお金を渡すかどうか?ということは、一種の洗礼として語られることがあります。
こういう物乞い達には、実は親玉が居て、非常に組織化されていたりするのです。
だから、お金を渡しても、彼らが搾取されるだけで、親玉が儲かるようになっている。さらにひどいことには、親玉が儲かるということは、次の犠牲者を増やす経済的な動機付けがあるということでもあります。物乞う子どもたちが創りだされたり、金を稼ぐために手足を切って捨てたりということさえ有ったとされます。(こういった現状はずいぶんと減ったと言われています)
社会の問題に立ち向かうということは、これと少し似ていて、「もぐら叩き」になってしまって、問題が何も変わらなかったり、もしくは、社会を良くしようとした結果、何か、誰かを傷つけるようなことが起こるということすらありえるわけです。冷静さと情熱、その二つが合わさって、ようやく社会の問題に向き合うことができるのかもしれません。冷静さだけでは、モチベーションが続かないし、情熱だけでは空回りすることもある。
新しい取り組みは、すぐには分かってもらえなかったりする。
こういう「問題をつくる仕組み」そのものに取り組もうとすると、すぐにはわかってもらえなかったりします。でも、「問題をつくる仕組み」を壊せたり、「問題の当事者が問題を解決する仕組み」をつくれたりすると、問題がぐぐぐーっと解決されたりするんです。
「仕組み」というとむずかしく聞こえるかもしれませんが、時にそれは、捉え方が変わるだけだったりします。アジア地域の地域活性化の代表的なアプローチの一つ「オンパク」や「一人一品」は「地域には面白いものがあるから、それを集めて見せるだけでいい」という小さな信念を大切にします。それが、結果として、大きな変化をもたらすのです。それが、「地域にはおもしろいものがあるわけない」という穿った思い込みを突き崩して、地域に新しいクリエイティビティが生まれる。
すごくシンプルで単純なアプローチなのですが、それでも、思い込みが変わるだけで地域や社会は変わったりすることがある。(大学時代をオンパク発祥の地、別府で過ごした僕は、その過程をまざまざと見せてもらったのでした)
こういうアプローチは決まって、「わけがわからない」「何のためにやるんだ」という抵抗にぶちあたることになります。でも、続けていくと、味方をしてくれる人が増えて行って、いつの日か結果が見せれたりする。結果が見せれると、それが、一回り大きな動きになって、社会や地域が少し動いたりする。
すぐにはわかってもらえるわけではないけれど、社会が変わる兆しや手応えに最初に出会える仕事なのだ、と思っています。
助けられる側だったから、もっと助けたい
こういう葛藤を選んだ理由はとても単純なことで、僕自身のアイデンティティが未だに、助ける側ではなくて、助けられる側にあるというシンプルなことなんです。だから、一人だけを助けるだけでは、自分の人生を終わらせることはできなくて。
さて、少し、「社会的投資」の話をさせてください。こういう葛藤に向き合う日々ですが、でも、それでも、社会を変えていける手応えがあるからこの仕事をしています。
「社会的投資」と書くと難しい言葉のように聞こえますが、配ることが目的化したお金に成果を求めたり、効率の良いお金の使い方ってあるよね、というだけの話です。つまり、良いお金の使い方をすれば、もっと社会は変わるから。それが財団を創ろうとしているたったひとつの理由です。
やろうとしていることは、本当に必要な時にお金を出すこと。対象とする人々にきちっと貢献していて、一緒に働く人達が充実している組織かどうか、訪れて確かめてみること。お金を自分だけが出すんじゃなくて、誰かがお金をさらに出したくなるような呼び水としての使い方をすること。
そして、お金をお預かりした方の本意に沿うようなプロセスをつくっていくこと。どうお金が使われたのか、ということわかったりするだけではなくて、できれば、その方自身が例えば、ライフワークとして、自分の新たな可能性を見出したり、そこから新しい未来の可能性が紡いでいけるような。
僕は、お金の出し手と受けての関係性が崩れたり、切れてしまっている今の資金の流れを変だなと思ってしまっていて。だから、コンサルティングを辞めて「社会的投資」を仕事にし始めたんです。
こういった「社会的投資」をやり始めるには、すごく時間がかかって、紆余曲折があったのですが、それは、また次回に。
=
前回はこんな記事を書きました。
■リスクについて
■WIA=World in Asiaという名前について
■財団が具体的に何をやるのか?
■これまでやってきたこと/やってこれたこと
■現場でよくぶつかるジレンマ
■それに対して、こうすればいいとおもっていること
ということもこれから書き綴っていければと思っています。
リターン
3,000円

財団設立時への参画の御礼として、
・フォトレター(財団設立時のみ発送)
・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。
- 申込数
- 27
- 在庫数
- 73
10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)
・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。
・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)
- 申込数
- 23
- 在庫数
- 77
3,000円

財団設立時への参画の御礼として、
・フォトレター(財団設立時のみ発送)
・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。
- 申込数
- 27
- 在庫数
- 73
10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)
・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。
・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)
- 申込数
- 23
- 在庫数
- 77

別府のレトロな温泉・東町温泉を改修し未来へつなぐ!!
- 現在
- 529,000円
- 支援者
- 54人
- 残り
- 23日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金
- 現在
- 7,221,000円
- 支援者
- 339人
- 残り
- 6日

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集
- 総計
- 100人
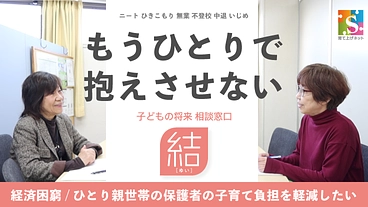
問題解決型の保護者相談を経済困窮・ひとり親世帯にも支援を届けたい
- 総計
- 77人

孤独な夜を照らす光を―家にいたくない若者の居場所をみんなで作りたい
- 総計
- 77人
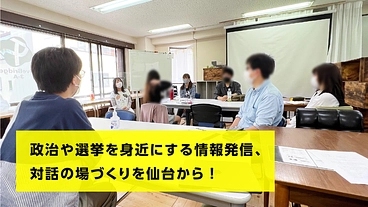
仙台発、政治や選挙を身近にする活動をサポートしてください!
- 総計
- 23人
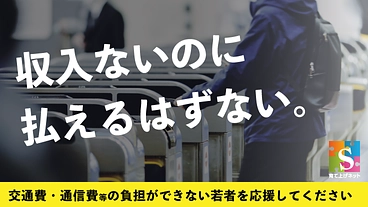
貧困・困窮状態にある若者の「実費」を肩代わり!継続支援のお願い
- 総計
- 77人