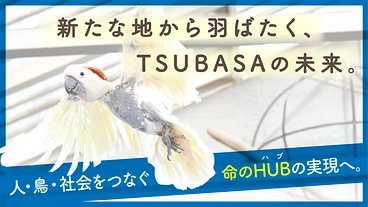支援総額
目標金額 10,000,000円
- 支援者
- 126人
- 募集終了日
- 2025年3月10日
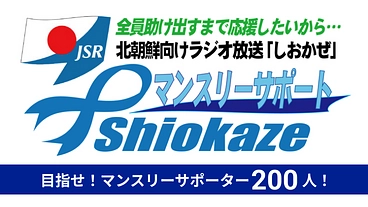
北朝鮮向けラジオ放送「しおかぜ」|マンスリーサポーター大募集
#人権
- 総計
- 165人
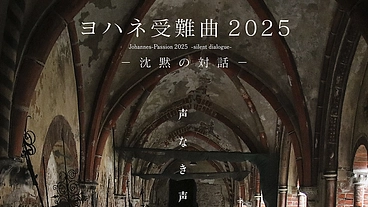
《ヨハネ受難曲 2025 −沈黙の対話−》 声なき声を聴くために
#音楽
- 現在
- 664,000円
- 支援者
- 92人
- 残り
- 11日
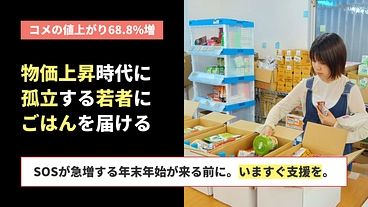
物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬
#子ども・教育
- 現在
- 11,484,000円
- 寄付者
- 306人
- 残り
- 30日

サポーター募集|沖縄久高島イザイホー映像アーカイブ化にご支援を
#地域文化
- 総計
- 32人

藤岡発!やよいひめの魅力を全国へ!第4回いちごフェスプロジェクト
#地域文化
- 現在
- 80,000円
- 支援者
- 6人
- 残り
- 42日
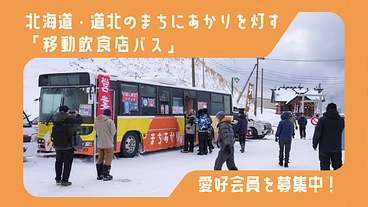
道北の街角に“あかり”をともす移動飲食店バスを未来につなぐ
#地域文化
- 総計
- 5人

日本一周経験者がご当地グルメを具に込めるおにぎりキッチンカーを運営
#地域文化
- 総計
- 0人
プロジェクト本文
終了報告を読む
▼「温故知新」の魅力を少しでも多くの方に知っていただけるよう、こちらの記事で本書の中身をチラ見せしています。下のバナーをクリックして、ぜひご覧ください!
銀座小十の料理長・奥田 透が立ち上がる。
我が国の宝 日本料理に、再度 “光” をあてるために。

世界では日本食ブームと言われています。しかし、肝心な日本では、その料理の伝統を理解し発展を担う若き人材が枯渇しはじめています。
料理業界のシェアはフレンチ、イタリアンなどの西洋料理が大多数を占め、日本の調理師学校の卒業生の9割は、フレンチ、イタリアン、パティシエ志望が現実です。
これでは近い将来、和食の基幹となる飲食店が衰退します。日本の食材の生産者、和包丁や砥石などの道具の職人、陶芸家、酒蔵などにも大きな影響が出てくるはずです。
つまり、日本の食の土台と根幹が大きく揺らぎ始めているのです。
これまで、私は、海外での日本料理店の出店や、寿司と和食だけの調理学校の開講・顧問就任など日本食の文化を途絶えさせないためにさまざまな取り組みを進めてきました。
しかし、まだまだ危機的な状況は続いています。
この課題の解決に向けて、まずは、日本料理を愛する人たちとともに、国内、そして世界にその魅力を広く伝えていくための専門誌「和の美 食の美 温故知新」を継続的に発刊したいと考えています。
発刊にあたって、編集委員に「dancyu」元編集長 町田成一氏、ライターの瀬川 慧氏など日本料理を愛する仲間の協力のもと、丁寧に取材や企画を作り上げてきました。
ただ書店に”日本食の専門誌”が置いてある状態を作りたいのではありません。
この状況を変えていくための“うねり”をつくりたいのです。
継続的な発刊と発信を続けていくため、そして応援してくださる方と繋がっていくため、クラウドファンディングというかたちで、皆さまのご支援を賜ることができればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
目次
・日本料理の未来を創り出すため、その魅力を発信する“媒体”をつくる
なぜプロジェクトを立ち上げたのか:
伝統が途絶えてしまうのか、日本料理に迫る危機
▍調理学校での生徒の割合は、和食と洋食で 1 対 9
2013年、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは、「和食」が料理のジャンルとしてだけではなく、南北に長く、四季が明確な日本の多様で豊かな自然と、そこで生まれた「食文化」として世界に広く認められたということです。しかし、このように世界から注目が集まる中、このままでは日本料理の文化や伝統が途絶えてしまうのではという危機感を強く感じています。
要因の一つは、調理師学校入学者の減少です。調理師学校の入学者は、就学人口の低下に伴い減少してきていましたが、コロナ禍を経てなお、その数値は下がり続けています。

ー2024年度「調理師養成施設入学者・留学生実態調査」データ発表ー 公益社団法人全国調理師養成施設協会
また、日本の調理学校は、フランス料理やイタリア料理などの料理人や、パティシエを育成することに重点を置く傾向があります。
データとしても10年前と比べて、日本料理の調理師認定証書交付の人数は約半分にまで落ち込んでいます。日本料理人になるためには必ずしも調理師免許が必要なわけではありませんが、鮨、天ぷら、そば、和菓子の道を選ぶ学生が圧倒的に少なくなっているという現場での実感もあります。調理師学校の改革をしなければ、和食と洋食の1対9の比率が、10年後は0対10になってしまうと危惧しているわけです。

ー厚生労働省「専門調理師認定証書交付数の推移」より抽出データをグラフ化ー
▍日本料理を知る、楽しむ媒体の変化。書店に並ぶ料理雑誌はいま...。
今回、最初のアクションとして雑誌制作に取り掛かかろうと決めた理由は、日本料理を扱う情報媒体(雑誌・テレビなど)の大きな減少を感じたことも背景のひとつです。
書店に行けば、料理専門誌コーナーに並ぶ表紙は、フレンチやイタリアンのシェフたちばかり。近年は、日本料理を専門に扱う雑誌はほとんど見なくなりました。お店でお食事を食べる以外でも、情報として手に取れる、興味を持つきっかけ自体も無くなっていることは大きな危機です。
何をするのか:
日本料理の未来を創り出すため、その魅力を発信する“媒体”をつくる
このような危機的な状況の中で、日本料理の未来を創り出す「人」を生み出すために、日本料理を理解し愛する人々をどんどん増やすために、今年、『和の美 食の美 温故知新』を立ち上げることを決めました。
日本料理を知ることはこの国自体を知ることであって、そして逆にこの国を示すものは日本料理で示すことができるのです。名前の「温故知新」には、「古きをたずねる、そして新しいものを現代に関わる人たちが作り上げていく」という想いを込めました。
【表紙】

【中身抜粋】
<概要>
監修:奥田透「銀座小十」
登場人物:
山本征治「龍吟」日本料理は国技である
齋藤孝司「鮨さいとう」私の鮨は私にしか握れない
石田知裕「膳司水光庵」日本料理の精神性を受け継ぐ
杉田孝明「日本橋蛎殻町すぎた」鮨屋という人生を選ぶ
前平智一「てんぷら前平」天ぷらでしか出せない美味しさを求めて
吉川邦雄「一東菴」蕎麦農家の特性を生かす蕎麦打ち
平山周「浅草ひら山」蕎麦店の伝統と日本料理の技の融合
浅沼努武「天ぷら浅沼」天ぷらほど楽しい料理はない
海原大「江戸前芝浜」江戸料理で江戸の“粋”を伝えたい
リオネル・ベカ「エスキス」海外から見た日本の食文化の魅力
櫻井真也「櫻井焙茶研究所」日本茶の価値観を伝え広げる
澤田裕介「子の日」料理人の覚悟を支える、ハレの日の和包丁
山口真人「陶芸家VS料理人」
長谷川浩一・あおい有紀「日本酒の50年と近未来」 ほか
出版社:誠文堂新光社
発売:2024年12月24日(火)
価格:4,180円(税込
先駆者の思いや生き様、守りたい伝統の技と心、そして新しい試みを紹介しながら、日本料理の世界がいかに素晴らしいかを真摯にお伝えしていきたいと思っています。
だからこそ、今回は日本料理に関わる入り口、大切に思う気持ちを「雑誌」という形にして多くの人と共有する機会を改めて作りたいと考えています。
私たちは、ただ書店に”日本料理の専門誌”が置いてある状態を作りたいのではありません。私たち日本人には、人類共通の財産となった「和食」を、その母国として、長く将来にわたり保護・継承していくことが求められています。そのため、この危機的状況を変えていくための“うねり”をつくること、それが今回の目的です。
継続的な発刊と発信を続けていくために、クラウドファンディングというかたちで、皆さまのご支援を賜ることができればと思っております。今回のプロジェクトは、資金面だけでなく、この活動を応援してくださるさまざまな方と繋がり、賛同者を増やしていくことも大きな目的のひとつです。
どうぞよろしくお願いいたします。
クラウドファンディング概要
第一目標金額:1000万円
資金使途:雑誌製作費、日本文化を未来に繋げていくための広報活動全般
※本プロジェクトは、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を自己負担するなどして、必ず上記の実施内容の通り実行いたします。
チームメンバー:
日本料理を愛するメンバーとともにプロジェクトを立ち上げます

「日本の食文化を守りたい」
この奥田透さんの想いに共感し、編集に携わらせていただいた。
私は平成2年(1990年)の創刊準備から30年余、食の雑誌「dancyu」で取材を重ねてきた。この間、日本酒、焼酎、すし、天ぷら、蕎麦、日本料理、和菓子などを特集する一方で、イタリアン、ワイン、スイーツの隆盛も体験してきた。
光陰矢の如し、歳月は人を待たず。
日々の享楽に身を委ねていたら、気がつくと日本の食文化の土台が大きく揺らいでいる。だから今回は、その反省も込めて、今の日本の食文化に正面から向き合う料理人さんや職人さんの声をお伝えすることから始めた。
以下は今回取材をさせていただいた、東京の東十条で「一東菴」という手打ち蕎麦の店を営む吉川邦雄さんの言葉だ。
「蕎麦の本当のおいしさは、農家さんの想いがあって初めて生まれると思っています。蕎麦という作物に込められた想いを受け止め、食べる方々に伝えるのが僕の役割。だから、直接、顔を見て、話を聞くことが欠かせません。さらに、そのとき目にした畑の景色や、吹き抜ける風、立ち上がる土のにおいまで蕎麦に打ち込みたい。それが味にも表れると信じているのです。
農業全般がそうであるように、蕎麦農家も高齢化は否めません。だからこそ、若く志の高い生産者を応援したい。今の僕にできるのは、蕎麦農家のみなさんの活力になる存在でいること。そして、同じ意識を持つ蕎麦屋仲間を増やして、蕎麦という文化のバトンを未来につなぐことだと思っています」
『和の美 食の美 温故知新』が、この一助になれば幸いだ。
応援をよろしくお願いいたします。
応援メッセージ:
このプロジェクトは多くの方にご賛同いただいています(※随時更新予定)
株式会社子の日 代表取締役 澤田裕介と申します。
プロの料理人が使う「包丁」を製作する仕事をしております。
20年以上前、特別な包丁の製作依頼をいただいたのが、奥田さんとの出会いです。
はじめて奥田さんのお店「小十」で食事をした時のことは今でも忘れられません。
自分の作った包丁が目の前で美しく活躍しているさまを見つつ、生涯最高の料理を食したその時に、僕が包丁職人として生涯の「やりたい事」が明らかになった気がしました。その時から僕にとって奥田さんは特別な料理人となりました。
日本料理とその空間は、時には人の人生に影響を及ぼすほどのコンテンツです。
この業界に少なからず関わりを持つ人間として、本物の日本料理を世界中の人に知ってもらい、楽しんでもらいたいと心から感じる様になりました。
日本料理は非常に奥深く、膨大な時間と経験、そして感性の上になりたつ類いの仕事です。
残念ながら世の中には表面的で、外観を模倣する様な情報が主体となってしまっていることに懸念を感じております。
このたび『和の美 食の美 温故知新』が発刊され、奥田さんが振る舞う様な、神髄ともいえる日本料理の技術、知識、心を多くの人が知る機会となり、それを若い人々が目指し、継承してくれる、そんなきっかけになる事を期待しております。
プロジェクトの成功を心からお祈りいたします。
ご注意事項
●本プロジェクトはAll-in形式のため、目標金額の到達有無にかかわらず当該活動を行います。
●ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。
●本ラウドファンディングへの支援金は、一般の寄付金としての取り扱いとなります。【個人の場合】所得控除・税額控除の対象とはなりません。【法人の場合】詳細は税理士にご確認ください。
●支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトの新着情報やSNS等発信などに利用させていただく場合があります。
●日時等について、調整の都合上、個別のご要望には沿えない場合がございますので予めご了承ください。
お問合せについて
ご支援方法やよくあるご質問については、READYFOR ヘルプページをご用意しております。
- プロジェクト実行責任者:
- 合同会社銀座小十(代表 奥田透)
- プロジェクト実施完了日:
- 2025年3月30日
プロジェクト概要と集めた資金の使途
雑誌製作費、日本文化を未来に繋げていくための広報活動全般
あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!
プロフィール
1969年静岡県静岡市生まれ。静岡、京都、徳島で約10年間、日本料理を学ぶ。29歳で地元・静岡に「春夏秋冬花見小路」を開店。2003年7月に東京・銀座に移り「銀座小十」をオープン。2011年8月銀座五丁目並木通りに「銀座奥田」をプロデュース。2012年6月同ビルに「銀座小十」を移転する。2013年9月フランス・パリにて「OKUDA」を開店。本物の日本料理を海外で提供するという挑戦を始める。著書に『世界でいちばん小さな三つ星料理店』(ポプラ社)、『焼く日本料理素材別炭焼きの技法』(柴田書店)、『日本料理銀座小十』(世界文化社)、『銀座小十の料理歳時記十二カ月献立にみる日本の節供と守破離のこころ』『銀座小十の盛り付けの美学徹底図解進化する日本料理とは何か』『銀座 小十の先付・付き出し 一〇一品』(誠文堂新光社)、『その料理、秘められた狂気』(ごま書房新社)ほか。
あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!
リターン
10,000円+システム利用料

日本料理の未来へ繋ぐ〜応援コース〜|10,000円
●お礼のメール
- 申込数
- 49
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年3月
30,000円+システム利用料
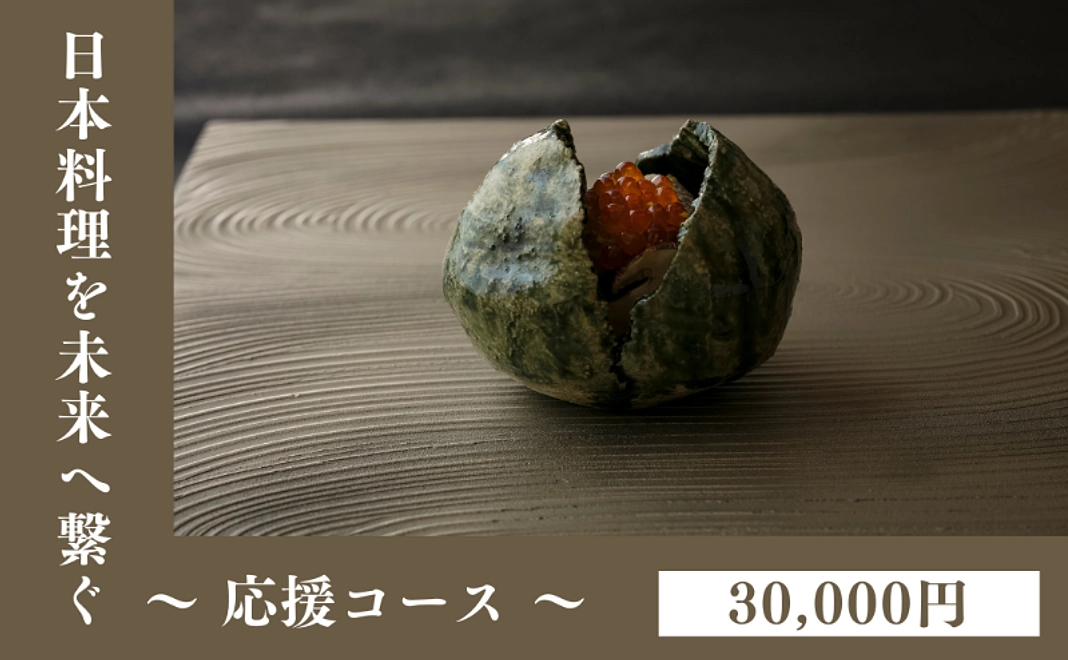
日本料理の未来へ繋ぐ〜応援コース〜|30,000円
●お礼のメール
- 申込数
- 18
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年3月
10,000円+システム利用料

日本料理の未来へ繋ぐ〜応援コース〜|10,000円
●お礼のメール
- 申込数
- 49
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年3月
30,000円+システム利用料
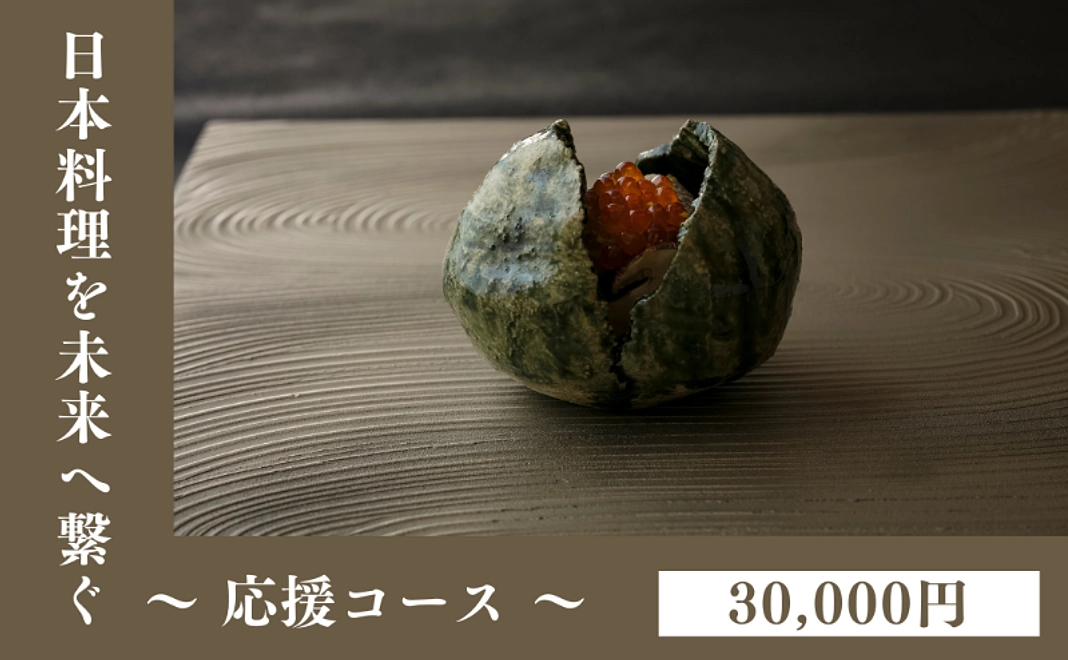
日本料理の未来へ繋ぐ〜応援コース〜|30,000円
●お礼のメール
- 申込数
- 18
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年3月
プロフィール
1969年静岡県静岡市生まれ。静岡、京都、徳島で約10年間、日本料理を学ぶ。29歳で地元・静岡に「春夏秋冬花見小路」を開店。2003年7月に東京・銀座に移り「銀座小十」をオープン。2011年8月銀座五丁目並木通りに「銀座奥田」をプロデュース。2012年6月同ビルに「銀座小十」を移転する。2013年9月フランス・パリにて「OKUDA」を開店。本物の日本料理を海外で提供するという挑戦を始める。著書に『世界でいちばん小さな三つ星料理店』(ポプラ社)、『焼く日本料理素材別炭焼きの技法』(柴田書店)、『日本料理銀座小十』(世界文化社)、『銀座小十の料理歳時記十二カ月献立にみる日本の節供と守破離のこころ』『銀座小十の盛り付けの美学徹底図解進化する日本料理とは何か』『銀座 小十の先付・付き出し 一〇一品』(誠文堂新光社)、『その料理、秘められた狂気』(ごま書房新社)ほか。

.png)