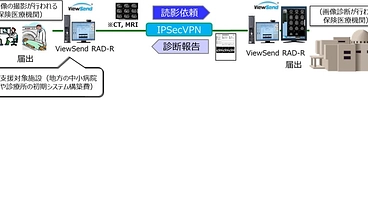支援総額
目標金額 400,000円
- 支援者
- 102人
- 募集終了日
- 2015年10月1日
「外れる」ことで見える世界~アメリカ文学は路上から始まった~
「文学」と「路上」はこれまでどんなかかわりを持ってきたのだろう? 私たちは「路上」からだけでなく、「文学」からの声も聞きたいと思いました。そう考えたときに、まず思い浮かんだのが、アメリカのビートジェネレーション(※)を代表する作家、ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード(旧訳のタイトルは『路上』)』です。そこで、この『オン・ザ・ロード』をはじめ、数々のアメリカ文学の翻訳を手がけてきた青山南さんに、アメリカ文学と路上の関係についてうかがいました。
※ ビートジェネレーション:アメリカで50年代に活躍した作家たちのグループ。体制や既存の価値観を否定した自由な表現は文学運動に発展し、若者や後のヒッピー世代から熱狂的に支持された。
<プロフィール>
青山南(あおやま みなみ):1949年生まれ。早稲田大学卒業。翻訳家、エッセイスト。現在、早稲田大学文学学術院教授。著訳書に『短編小説のアメリカ52講』『オン・ザ・ロード』(ジャック・ケルアック著) 『O・ヘンリー ニューヨーク小説集』(O・ヘンリー著)ほか多数。
*************************************

青山:アメリカ文学の長い伝統のひとつとして、「放浪者の文学」というものがあるんです。そもそもピルグリム・ファーザーズと呼ばれる、イギリスからアメリカに最初に渡ってきた清教徒(ピューリタン)たちが東海岸にたどり着いたときには、もちろん家なんてありません。アメリカに渡って来たばかりの人たちにとっては、「家がない(ホームレス)」というのは当然の状態。そこからホームを探して西へ西へと移動していく、というのが彼らの生き方でした。つまりアメリカ文学は、その移動する「路上」から始まったと言えるのです。
「HOBO(ホーボー)」(※)という言葉がありますが、それはいまもアメリカ文化のなかに根付いています。かつてホーボーたちは、鉄道の貨車に無賃乗車して移動しました。貨車の扉を開けると他のホーボーがいて、「どこから来たの?」と会話が始まったり、彼らを取り締まる鉄道の公安官と追いかけっこをしたり……。こうした情景はアメリカの文学や映画のひとつのパターンとしてあちこちで描かれています。道路が整備され、車が登場してくると、今度はヒッチハイクが中心になって、トラックの荷台に乗り合い、各地に仕事を求めて移動していきました。そうしたホーボーとか、「transient(トランジエント)」、などと呼ばれた移動する労働者が、アメリカには非常にたくさんいたのです。
※ ホーボー:19世紀終わりから20世紀初めにかけて、世界的な不況の時代にアメリカ各地を渡り歩きながら働いていた労働者のことを指す。
――仕事を求めて各地を移動する労働者の姿は、いまの日本の路上にいる人たちとも共通する部分がありそうです。当時はやむを得ない事情で移動していたのでしょうが、そうしたホーボーの精神が、その後のアメリカ文化にも影響を残していくのですね。
青山:日本と決定的に違うのは、土地が広いこともあって、「移動」そのものに楽しみや生きがいを見出していることです。A地点からB地点へと移動していく、その途中に出会いやストーリーがあるのです。今では、アメリカでのヒッチハイクは禁じられているのですが、高速道路の入り口あたりには、やっぱりまだ行き先を書いた紙を持った人が立っているんですよね。“Anywhere but here”(ここではないどこかへ)というのは、アメリカ文学を理解するための大事なキーワードですが、行き詰まったら「オン・ザ・ロード(路上)」に出てみるという精神は、アメリカ人にとっては一種のDNAのように残っているのだと思います。
――ケルアックの小説のタイトルである「オン・ザ・ロード」というのは、路上に留まっているのではなく、移動している状態のことを意味するのですね。そういえば、この路上文学賞の主宰者のひとりである作家の星野智幸さんは「“ホームレス”と呼ばれる人たちはずっと路上にいるわけではなく、これからどこかへ行く途中の人たちなんだ」と話していました。
青山:そう考えると、共通点があるかもしれないですね。アメリカの路上で生まれた文学や映画は、いまやロードノベルやロードムービーとして世界中に広まっています。普通の文学作品には、いわゆる話の展開があるわけですが、路上を移動しながら生活している人たちには、次に何が起こるかわからない。プロットがないし、話の展開がみえない。ころころとストーリーが変わるので、それが人をひきつける。つながりのないストーリーをいくつもつなげることで長編になるのですが、それぞれを切り離せば短編になります。アメリカで短編小説が発達したのには、そういう理由があるんです。
――プロットのない短編がいくつもつながって長編になるというのは、まるで人生そのものを表しているようです。ケルアック以外に、放浪や路上の文学の代表的な作家というとどなたがいますか?
青山:アメリカ文学の源流、ウォルト・ホイットマンは放浪文学の筆頭にあがります。「Song of the Open Road(オープンロードの歌)」は、ずっとつながっていく道について歌っている作品です。代表的な詩集『草の葉』でも、とにかく路上に出よう、と歌っています。『トム・ソーヤーの冒険』で知られるマーク・トウェインも、アメリカ中を放浪する旅行記をたくさん書いていますし、ほかにも、ジョン・スタインベックだとか、O・ヘンリーの作品のなかにも、いろいろなものを見聞きしてきた存在として、放浪者やホームレスの人たちが出てきます。
たとえば、O・ヘンリーの短編『The Making of a New Yorker(ニューヨーカーができるまで)』の冒頭は、こうなっています。「tramp(放浪者。浮浪者の意で使われることも)」を全面的に肯定していますよね。
〈ほかの多くのことを別とすれば、ラグルズは詩人だった。彼は放浪者(tramp)と呼ばれていたが、それは彼が哲学者で、アーティストで、旅人で、ナチュラリストで、発見者でもあると言うときの省略した言い方にすぎなかった。ともあれ、なによりもまず彼は詩人だった。生まれてこの方、詩は一行たりとも書いたことがなく、彼は彼の詩を生きていた。彼の一代放浪記は五行戯詩になっていただろう、もし書かれていればの話だ。ともあれ、第一命題にあくまでもこだわるとすれば、ラグルズは詩人だった。〉
(路上文学賞実行委員会・訳)
また、思想家であり、博物学者、詩人でもあるヘンリー・D・ソローの『ウォールデン 森の生活』という有名な作品もあります。森のなかに丸太小屋をつくり、自給自足で暮らした生活についてまとめたものです。放浪とはちょっと違うかもしれないですが、「正規の生活から外れる」ことの大切さを提案している点では同じです。
――「外れる」ことで見えてくるものがある。逆に言えば、正規の生活をしているだけでは見えないものがあるという考え方なのでしょうか。こうした思想は、現代のアメリカでも生きていますか?
青山:現代のアメリカでは、資本主義的な価値観のほうが主要です。「あなたは何をしている人?」と訊かれて、「詩を書いている」とか「絵を描いている」と答えたら、「それはいいけど、どうやって生活しているの?」と訊かれるでしょう。文化的・精神的なことよりも、いまは「お金をどうやって稼いでいるのか」ということが、何よりも重要な価値になっています。これは、いまの日本でも同じかもしれません。
その一方で、移動そのものを楽しむような人たちも伝統的にいて、そういう人たちは、アメリカの支配的な価値観から自由に逃れているともいえます。いわゆる「ドロップアウト」の思想が花開くのは60年代になってからですが、その源流はホイットマンとかソローのなかにあるし、もっと無理やり遡れば、イギリスからはみ出すことになったピューリタンの人たちのなかにあったということになるのでしょう。
路上にいる(オン・ザ・ロード)人たちは、「どうやって稼いでいるの?」と訊いてくるような資本主義的なアメリカ人から見れば、「外れた人たち」かもしれませんが、そうした人たちを高く評価するまなざしは、いまもアメリカの文学やアートの世界には少なからずあります。
――アメリカでは「文学」と「路上」は深いつながりがあることがわかりました。日本にも、O・ヘンリーが言うような「まだ書いたことのない詩人」が路上にたくさんいるのかもしれません。「路上文学賞」からどんな作品が生まれるのか、ますます楽しみになりました。貴重なお話をありがとうございました。
リターン
3,000円

・路上文学賞・受賞作品集1冊
・路上文学賞・受賞作品集に支援者としてお名前を掲載
・サンクスレター
- 申込数
- 62
- 在庫数
- 制限なし
5,000円

・路上文学賞・受賞作品集3冊
・路上文学賞・受賞作品集に支援者としてお名前を掲載
・サンクスレター
- 申込数
- 23
- 在庫数
- 27
3,000円

・路上文学賞・受賞作品集1冊
・路上文学賞・受賞作品集に支援者としてお名前を掲載
・サンクスレター
- 申込数
- 62
- 在庫数
- 制限なし
5,000円

・路上文学賞・受賞作品集3冊
・路上文学賞・受賞作品集に支援者としてお名前を掲載
・サンクスレター
- 申込数
- 23
- 在庫数
- 27

夜の世界で孤立している人たちに、AIの力で「明日の選択肢」を届ける
- 現在
- 4,665,000円
- 支援者
- 118人
- 残り
- 27日

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を
- 現在
- 1,628,000円
- 寄付者
- 222人
- 残り
- 8日
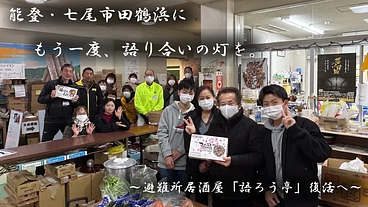
被災地・七尾市田鶴浜に 再び賑わい・語り合いの場を
- 現在
- 972,000円
- 支援者
- 52人
- 残り
- 8日
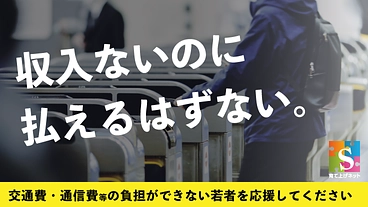
貧困・困窮状態にある若者の「実費」を肩代わり!継続支援のお願い
- 総計
- 77人

ゆきねこサポーター募集中|保護猫シェルター幸せの家へご支援を
- 総計
- 111人

“鉄道を撮る、鉄道に乗る”を楽しむ活動で鉄道会社を応援したい!
- 総計
- 43人

生活に困窮しているひとり親家庭の子どもたちに毎日お弁当を届けたい!
- 総計
- 10人