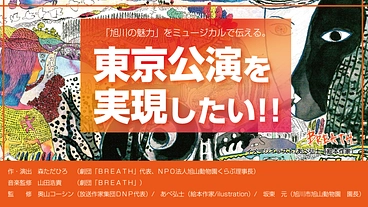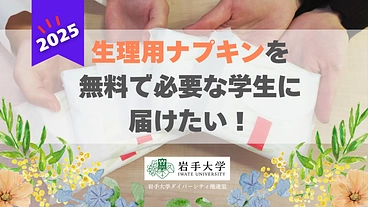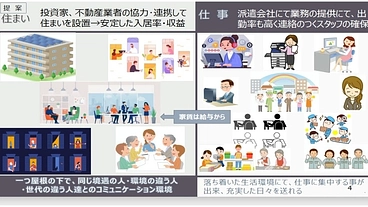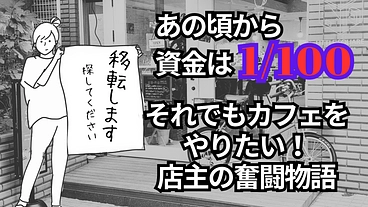支援総額
目標金額 470,000円
- 支援者
- 35人
- 募集終了日
- 2020年8月5日
農業と水産業との折り合いをどのように考える? その3
ちょっと硬い文章が続きます。農業と水産業との折り合いのためには、地域での合意形成が必要です。それがどのように行われてきたかについて書かれています。
ご参考になりましたら幸いです。
元のアドレスは、
になります。
7.総括
7.1.総合討論
北海道根釧地方は,1910 年ごろの殖民地区画開放から始まる農地開発によって,台地上の大部分は草地化され,森林面積率は減少した。森林面積率の減少は,鳥類においては森林種を減少させ,林縁種,草原種が増加したと考
えられる。また,バイカモは西別川上中流域に生息しているが,草地化が進行した中流域では群落の消滅も見られている。
草地化された北海道根釧地方は,草地酪農地帯となった。1970 年代以降,乳生産量拡大を目的としてha 当たりの乳牛飼養頭数の増大が行われ,それに伴い化学肥料と購入飼料の消費量が増大した。このことは河川流域の窒素投入量を増加させ河川水中の硝酸態窒素濃度を増大させた。河川水中硝酸態窒素濃度の増大は酸可溶Al 濃度およびアルミノン反応性Al(イオン態Al)濃度を増大させた。イオン態Al 濃度は,サケマス稚魚の半数致死量に相当する0.13mg/l を超える調査地点も確認され,現実的な脅威であると考えられる。そしてこ
のことは,バイカモにも同様な影響を与えている可能性が考えられた。また,河川流域の森林面積率の減少(草地面積率の増加)は,草地由来の堆厩肥,スラリー等の河川への流入を増加させたと考えられ,COD 濃度を増加させDO 濃度を低下させた。
このように,河川水中のイオン態Al 濃度の増加と河川水中DO 濃度の低下は,サケマスをはじめとした河川水生成物に大きな影響を与えたと考えられた。
酪農開発による森林面積の減少と河川流域窒素投入量の増大が,河川水質を変化させた可能性について論じた。また,河川流域窒素投入量は化学肥料や購入飼料の消費量に左右されることを明らかにした。
西別川の河川水質に関しては,サケマス稚魚の半数致死量とされるイオン態アルミニウム濃度が0.13mg/l を超える本流及び支流が存在する(橋本1989)ことが明らかになった。
そこで,河川水のAl 濃度や河川水Al の由来と考えられる土壌のAl 濃度が,河川流域の土地利用や酪農生産構造によってどのように変化するかをまず明らかにした。
具体的には,河川水質の相互関係を確認し,河川流域土地利用と河川水質の関連を確認した。そして河川流域の物質投入と河川流域の土壌の関連,河川水質の関連を明らかにした。
次に,河川水のAl 濃度や土壌中のAl 濃度が,水生生物および草地植生に与える影響について検討し,具体的には,酪農生産構造による草地への物質投入の変化を確認し,草地への質投入の変化によって草地植生がどのように変化するかを検討した。また,草地に投入された物質がどのような経路で河川へ流出するかについて検討した。
そして実験的に土壌に窒素肥料を添加し,土壌中のイオン態Al の変化について検討した。また,実験的にイオン態Al 濃度を変化させ,チモシー幼苗の変化,土壌枯草菌の変化,バイカモの変化を確認した。その上で,水生生物および草地植生とイオン態Al 濃度との関連を明らかにして,流域管理のありかたを考えていく科学的な枠組みを構築することを目的とした。
そこでサケマス稚魚の半数致死量であるイオン態Al 濃度0.13mg/l 以下にする流域管理を第一段階の管理目標値として,どのような管理を行うべきかを論じた。
人為的窒素投入量削減,草地土壌の改良,河畔林復元の3 つが重要なポイントとして浮上した。
第一段階の管理目標値を維持するためには,人為的窒素投入量を80kg/ha を限度とし,硝酸態窒素というアニオンの発生を抑制すること,草地土壌の塩基飽和度を上昇させるため土壌交換性CaO を400mg/100g 乾土以上にすること,河川水中硝酸態窒素を抑制するために流域森林率を40%程度に維持すること,の3 つのいずれかを満たすことが条件と考えられた。
しかし,人為的窒素投入量の抑制は生産乳量の抑制も意味することから,地域経済全体への負の影響も大きい。また,流域森林率の増加は草地面積の減少を意味することから植林地の確保が難しい。流域草地土壌の塩基飽和度を増加させるためには炭酸カルシウムの購入と施用が必要になる。いずれにしてもコストの発生や地域経済全体への影響が考えられることから,コンセンサスを得るために,地域住民自らリスク管理を行うための調査分析を行い,情報を地域住民,行政,JF,JA,関連産業などが共有し,地域全体で今後の方向性を考えていく場の必要性についても述べた。
これらを具体的に展開していくためには,根釧地方において現在までどのような動きがあったのかについて振り返る必要がある。
酪農開発による自然環境への負の影響は,1960 年代後半から地域住民から指摘されてきた。1960 年代後半から1980 年代にかけて活動した根室自然保護教育研究会では,草地開発に伴う森林面積の減少と化学肥料および購入飼料の使用量増大により,野生生物へ負の影響が発生していることを繰り返し指摘していた(三浦1974)。鳥類標識調査の継続的な実施により,アオジ等の林縁種・草原種が増加している可能性が高いことを指摘したのもこの団体の活動であった(三浦1974,阿部ら2008)。
一方,酪農開発による河川環境や水産業への負の影響も,1960 年代後半から地域住民の手によって明らかにされてきた。影響を受け取る側である水産業関係者の行動も,早い時期から始まっていた。別海漁業協同組合青年部の活動により,根釧地方の多くのサケマス増殖河川において水産用水に適さない河川が多く存在する事実を明らかにしてきた(根室管内漁協専務参事会1976,根室地区水産技術普及指導所標津支所2003,八戸2009)。
また影響を与える側である酪農民自身からも,酪農開発による1 戸当たりの大規模化,いわゆるゴール無き拡大による酪農民自身の疲弊・経済的逼迫について問題視するようになった。1970 年代には別海労農学習会が開催され,ここですでに「誰にも振り回されずにマイペースに酪農を続けていくにはどうしたらよいのか」という問いかけがあった(吉野2008)。これが後の1990 年代に大きく展開するマイペース酪農運動に発展していく(三友2000,吉野2008,酪農の未来を考える学習会2009)。
このように,1960 年代後半から地域住民の間ではそれぞれの立場で際限なき酪農開発への異議申し立てが存在した。しかし影響を与える側の指導的立場にある農政および農業試験研究機関は,地域全体の乳生産量のさらなる拡大を阻害するものとして認識したため,政策的および科学的知見を基に抑え込みを図った。
政策的には,化学肥料及び購入飼料の低価格化を推進し,買取乳価の安定を図ることで,農業粗収益に注目した経営,つまりは乳生産量の拡大が農業所得を増大させる経営にシフトやすい環境を整えた(岩崎2006,畠山2009,岩崎2010,吉野2008,佐々木2014,佐々木2017)。
さらに環境への負の影響に関しては,以下のような論を展開し,根釧地方には環境問題は発生していないとの論陣を張った。これらの論の基調は,水産用水基準ではなく水道水質基準を採用したこと,その論拠としてEU の規制を引用していることによる(Smith et.al 1993,ブリン1999)。
松中らは,収穫物によって収奪された土壌養分を,何らかの形で還元しなければならない。これが循環農法の基本であるとして,酪農ではその土地から生産される自給飼料の生産量で飼養可能な乳牛を飼養し,その排泄物を土地に還元することが基本であるとしている。その一方で,都府県では余剰窒素354kg/ha,北海道では100kg/ha であり,窒素環境容量(自然の自浄力によって窒素による環境への悪影響が生じないような環境の収容力)を200~
250kg/ha であると提唱(2 頭/ha)し,北海道は環境容量以下のため,余剰窒素による地下水汚染の可能性は低いとした(松中ら2008a,松中2008b,岡本2008、中辻2008、中辻2009,三枝ら2008,大塚2009,北海道農政部道産食品安全室2003,北海道農政部食の安全推進室食品政策課2005)。
しかしながら,現実に水産用水基準を超える河川水が確認された。それにもかかわらず環境汚染の可能性は低いとした原因は,農政および農業研究機関側が水道水質基準のみで考えているためであった。つまり,水産用水基準は富栄養化防止の観点から全窒素1mg/l 以下を求めているのに対し,水道水質基準は人体への硝酸塩中毒防止の観点から硝酸態窒素10mg/l以下としており(Smith et.al1993),この10 倍の差が地域住民との議論をかみ合わなくしている要因であった。
一方で,循環農法に立ち返ることを目標とした研究も存在した(干場2007,干場2008a、干場2008b,干場2008c、干場2008d,猫本2008,仙北2008)。しかし,食品の安全性への議論,酪農経営改善への議論,環境負荷をできる限り低減することは説いたが,地域課題の具体的把握と解決策の設定には至らなかった。
また農政と農業試験研究機関では,現実問題として発生している液状厩肥による臭気対策として,スラリーインジェクタの普及を図った。しかし,スラリーインジェクタの使用は,地下10 ㎝程度に液状堆厩肥(スラリー)を注入するため,強度の降雨時の表層流去由来の河川水有機物,窒素等は減少させると考えられるものの,平水時は地下5 ㎝以下の土壌水が河川水へ移行すると考えられるため,平水時の河川水中硝酸態窒素は上昇する可能性がある。また作業速度が遅く機械は高価であり,酪農経営としてもメリットが少ない。なによりも流域窒素投入量には変化が生じないため,余剰窒素の削減にはほとんど貢献しないという弱点があった。
このように,農政および農業研究機関の意向と地域住民の意識は噛み合わない状態が続いてきたが,このような状況下においても,地域住民は風穴を開けるべく活動を続けていた。
1990 年代後半から,別海漁業協同組合青年部の流れをくむ虹別コロカムイの会による西別川流域コンサートや河畔林復元に向けた植樹活動が行われるようになった。また,摩周水環境フォーラムを開催し,実際問題としての環境悪化を指摘し続けるとともに,様々な研究機関,行政との連携を図った(虹別コロカムイの会2016)。
マイペース酪農においても,荒木の先行研究から酪農経営におけるマイペース酪農は,中小規模ながら生産コストを圧縮し,低い農業粗収益でも生活に十分な農業所得を維持していることが明らかにされた(荒木1992a,荒木1992b,荒木1992c)。このころ三友農場の参加により,三友農場がマイペース酪農のモデルとしての位置を占めるようになり,生産現場からの経営の理論化が進んだ。三友氏の著作による,マイペース酪農の言語化および理論化が
行われた(三友2000)。さらに経営的側面からの集大成として,吉野がマイペース酪農の経営的有利性を立証した(吉野2008)。
リターン
10,000円
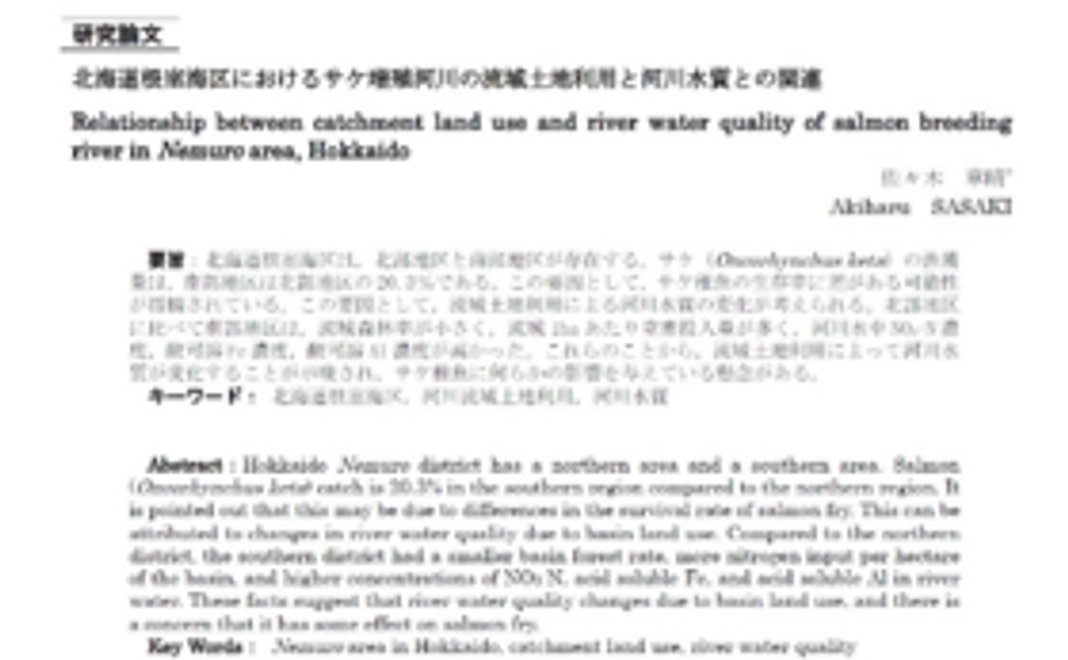
土と水を保全する研究成果2020
このプロジェクトで明らかになった研究成果・データを,支援者の皆様にご提供いたします。データの活用は特に制限を設けないこととします。メール添付をご希望の場合は、メールをご選択ください。郵送をご希望の方は、郵送をご選択ください。郵送でお送りします。
- 申込数
- 49
- 在庫数
- 50
- 発送完了予定月
- 2021年3月
10,000円

ニシベツ伝記(小説)
今までの研究成果を小説化してみました。
架空の根釧原野に存在する、付属短期大学を持つニシベツ実業高校を舞台として、地域の課題を生徒たちが解決していく、と言ったストーリーです。
- 申込数
- 1
- 在庫数
- 99
- 発送完了予定月
- 2020年10月
10,000円
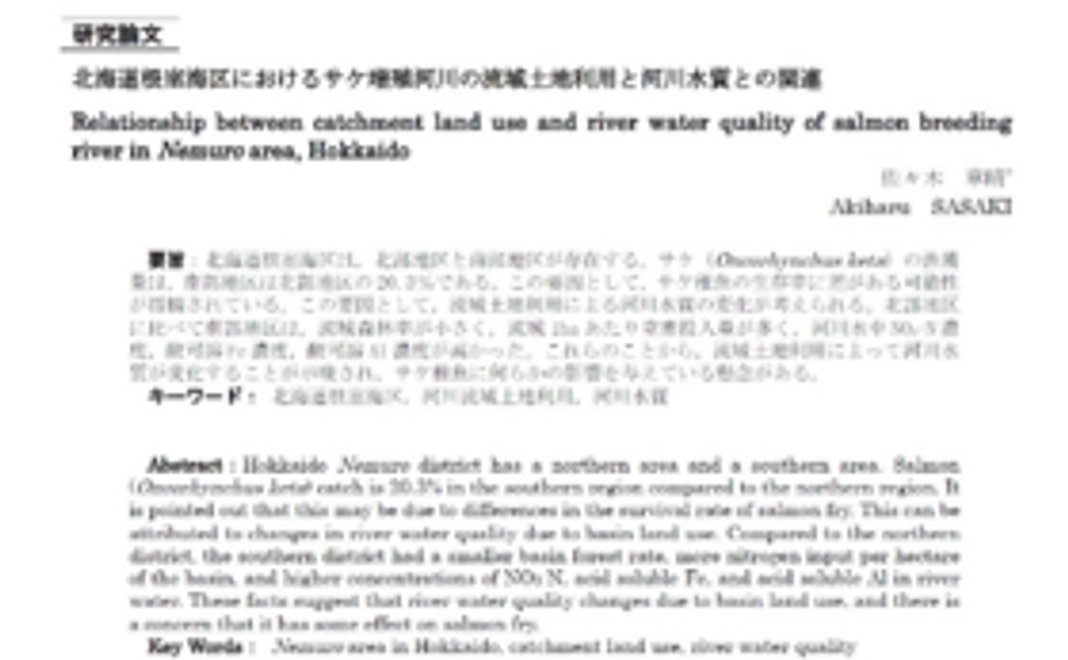
土と水を保全する研究成果2020
このプロジェクトで明らかになった研究成果・データを,支援者の皆様にご提供いたします。データの活用は特に制限を設けないこととします。メール添付をご希望の場合は、メールをご選択ください。郵送をご希望の方は、郵送をご選択ください。郵送でお送りします。
- 申込数
- 49
- 在庫数
- 50
- 発送完了予定月
- 2021年3月
10,000円

ニシベツ伝記(小説)
今までの研究成果を小説化してみました。
架空の根釧原野に存在する、付属短期大学を持つニシベツ実業高校を舞台として、地域の課題を生徒たちが解決していく、と言ったストーリーです。
- 申込数
- 1
- 在庫数
- 99
- 発送完了予定月
- 2020年10月

「なまけものの通りみち」となる生物回廊農園を共に作り育てましょう!
- 総計
- 58人

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を
- 現在
- 1,628,000円
- 寄付者
- 222人
- 残り
- 9日

フィリピン・セブ島沖地震|命をつなぐ緊急支援
- 現在
- 186,000円
- 寄付者
- 34人
- 残り
- 9日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!
- 総計
- 38人
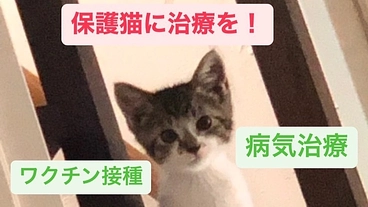
保護猫ーワクチンや病気治療のご支援をお願いしますねこ
- 総計
- 3人

「ヒグマ対策×ドローン調査で地域の安心を守りたい」
- 現在
- 13,500円
- 支援者
- 3人
- 残り
- 15日