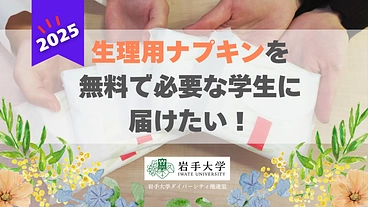支援総額
目標金額 15,000,000円
- 支援者
- 783人
- 募集終了日
- 2024年4月26日
戦車改造ブルドーザーの実態は?(2010年執筆記事より転載)その2
プロジェクト概要に記載した丹羽次郎さんとの出会いにより、更生戦車に興味を持った実行者が2010年に執筆した記事を特別に転載致します。本当なら「日本陸軍の戦車(カマド出版)」をご購入頂くのが一番なのですが、絶版となって久しくプレミア価格になっております故・・・
長くなるので2回に分けてご報告させて頂きます。とうことで、後半となる記事その2は今回のプロジェクトにも繋がる北海道のエピソードです。

北海道の鉄牛
現在では会社がどこにあったのかも分からない、丹羽次郎氏が勤めていた「共同建設」と対照的な会社が、北海道札幌市内に本社を構える「中山組」である。
大正12年設立の「中山組」は2代目中山弘三社長が土木事業に機械力を導入することに熱心で、戦後の復興事業に取り組む中で戦車改造ブルドーザーの導入を図る。
「そりゃ、それまで鍬とモッコでやってたんだもの、一目で惚れちゃったよ」と語る、平成22年現在、滝川市在住の山内正次氏は昭和4年生まれの81歳。「開発庁長官が見ている前で粘土にハマって動けなくなっちゃうんだもの、ブルドーザーといっても戦車だからね、キャタピラが細いの。」と、当時を振り返る同じく札幌市在住の中島隆氏は昭和5年生まれの80歳。両名にお話を伺う中で、おぼろげながら三菱で改造されたブルドーザーの流通ルートが見えてきた。
「中山組」に更生ブルドーザーが導入されたのは昭和24年9月のことで、そこには旧日本軍戦車隊の藤中護氏(陸軍軍曹、終戦時択捉島にてソ連軍に降伏、シベリヤ抑留を生き延びて、昭24年に「中山組」入社)の人脈と行動力が際立つ。藤中氏は戦時中の人脈を頼って東京三菱製作所に直接赴き、一台50万円で更生ブルドーザーを購入したという(昭和24年当時の大学初任給は4223円)。その後も順次導入され、合計3台から5台のチハ改造ブルドーザーを使用したそうだ。「中山組」が購入した更生ブルドーザーはすべて「高座式」であり、このことから「低座式」は極初期に少数が改造されたものと思われる。
前述の丹羽氏と、ちょうど入れ替わる時期に稼働を始めた北海道のチハ改造ブルドーザーは、戦後の混乱期を脱しつつある中で、会社が機械化に積極的なだけではなく、機械工学に造詣の深い経営者のもと藤中元陸軍軍曹の采配もあり、バッテリーやオイルなどの補給物資調達も順調で稼働率は高かったそうだ。しかし故障は多く、こちらでも履帯ピンの損耗は激しく、べベルギヤーの欠損も多かったそうで、その都度東京方面から部品を調達し、エンジンオイルについては100時間ごと、約1カ月に2回程度実施していた。
「次の現場への移動は早かった。元が戦車でしょ。道路と言っても当時は舗装されてないし、トラックだって追いつけないくらい凄かったね。」とは中島氏の談。しかし、ブルド-ザーとしては役立たない高速走行向けのギヤー比は現場では不満だったようで、「歯が欠けたベベルギヤーを変えるには重たい変速機を下してね、それからじゃないと交換できないの。大変だったよ。それでベベルギヤーを作り替えることになったの」山内氏によると、地元の工業所に依頼して、ベベルギヤーを新造し、ギヤー比を上げて負荷を下げるという本格的な改造も施したそうだ。さらに24ボルト電装の車両が必ず2台で現場に出て作業し、万が一のバッテリー上がりのときにはジャンピングケーブルでの始動を考慮したり、零下30度になる真冬の現場では始動一時間半前から車体下部から練炭で熱するなど、最前線を経験した下士官が仕切る現場ならではのエピソードも伺えた。
写真左が山内氏、右が中島氏(2010年中山組本社にて撮影)
道路工事や河川改修工事に活躍し、初代北海道開発庁長官が現場見学し賞賛されたチハ車改造ブルドーザー達であったが、北海道においても昭和20年代後半には進駐軍払下げのブルドーザーや国産ブルドーザーの導入が進み、昭和30年ごろにはすべて更新されてしまったそうだ。導入時期と違い、廃車になった時期ははっきりしないが、最後の様子は判っており、すべての車両が鉄くずとして、溶断され鉄くず業者に出されてしまったとのこと。高度経済成長に向かう日本が一番元気だった時代、古くなったら捨てられるという当たり前の運命が戦車改造ブルドーザーを待っていた。「無意識だったと思うけど、やっぱり長く使った車両が切られるのは見たくなかったのかな、車両課でガス溶断されることは知ってたけど見た覚えがないもの。」山内氏が最後の時期をはっきり覚えていないのはこのためで、氏の脳裏にはいまもディーゼルエンジンのエキゾーストノートを響かせ走る、チハ改造ブルドーザーが焼き付いているのだそうだ。
昭和30年と言えば、東京では陸所幕僚監部から中特車に関する開発目標案が示され、戦後初の国産戦車(後に61式戦車として制式化)の開発が始まった年である。日本の戦車開発史において、戦前から戦後の空白期間などと言われる時期もチハは国土復興のため走っていた。老兵は死なず、ただ去りゆくのみ・・・戦後復興の一翼を担い、役目を終えた更生ブルドーザー達はこの時期に日本各地で同様な最後を迎えたのだ。*「日本陸軍の戦車」カマド出版(2010年発行)より転載
【みなさまにお願いです】
冒頭に記したとおり、2010年に実行者小林がお伺いしたエピソードを一部表現を修正し、前回と今回の活動報告でご紹介させて頂きました。この記事が切っ掛けとなり、北海道の支援者様から一枚の写真が届いたことで今回のプロジェクトはスタートしました。そしてこの度最終段階(最終段階とは九五式軽戦車改造ブルドーザーの修復と、修復過程でのオリジナル車両の製造工場や製造時期の特定に繋がる情報調査です。)に入った本プロジェクトですが、取り扱い車両が地味なのか?我々の情報発信が弱いのか?目標金額へ向けた進捗がこれまでのプロジェクトに比較して遅れております。
今回のクラウドファンディングで目標に手が届かないとこれらの調査、修復に取り掛かることが出来ません!何卒、ご支援を検討中の方は出来るだけ早いご支援実行を、すでにご支援実行済みの方には、一人でも多くの方に今回の修復・調査プロジェクトをお知らせ頂けるようにお願い致します。
実行者:小林 雅彦
リターン
5,000円+システム利用料

感謝のメールコース
●感謝のメール
●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告
●お披露目会ご招待(1名様)
【お披露目会ご招待】
会場:御殿場市内の博物館建設候補地
実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定
詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで
会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。
- 申込数
- 236
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月
10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース
●オリジナルポストカード
●感謝のメール
●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告
●お披露目会ご招待(2名様)
【お披露目会ご招待】
会場:御殿場市内の博物館建設候補地
実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定
詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで
会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。
- 申込数
- 266
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月
5,000円+システム利用料

感謝のメールコース
●感謝のメール
●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告
●お披露目会ご招待(1名様)
【お披露目会ご招待】
会場:御殿場市内の博物館建設候補地
実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定
詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで
会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。
- 申込数
- 236
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月
10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース
●オリジナルポストカード
●感謝のメール
●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告
●お披露目会ご招待(2名様)
【お披露目会ご招待】
会場:御殿場市内の博物館建設候補地
実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定
詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで
会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。
- 申込数
- 266
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!
- 総計
- 530人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ
#伝統文化
- 現在
- 61,720,000円
- 寄付者
- 2,857人
- 残り
- 29日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ
- 現在
- 73,930,000円
- 支援者
- 6,385人
- 残り
- 32日
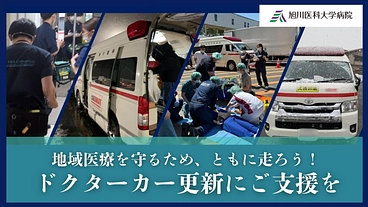
地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト
- 現在
- 7,233,000円
- 寄付者
- 256人
- 残り
- 29日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ
- 現在
- 25,452,000円
- 寄付者
- 297人
- 残り
- 28日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 217,305,000円
- 支援者
- 12,338人
- 残り
- 29日
おおきなことゆくラックを作りました!高学年向けランドセル
- 支援総額
- 1,026,230円
- 支援者
- 32人
- 終了日
- 2/25
「100人がつなぐBabyDress1着のSTORY」を創りたい!
- 支援総額
- 1,003,600円
- 支援者
- 104人
- 終了日
- 3/14

がんと向き合う家族の笑顔とStoryで希望を届ける!写真展開催へ
- 支援総額
- 1,006,000円
- 支援者
- 108人
- 終了日
- 1/27

“A5”仙台牛をおうちで!仙台牛を食べて応援プロジェクト
- 支援総額
- 2,255,000円
- 支援者
- 121人
- 終了日
- 12/11
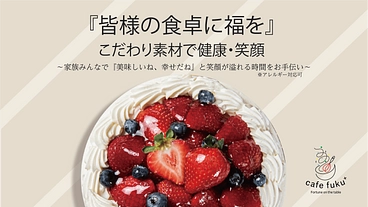
『皆様の食卓に福を』 笑顔・健康・幸せな時間を届けるお店を開業!
- 支援総額
- 1,070,000円
- 支援者
- 58人
- 終了日
- 9/29
2023年観光業界・地域活性化の未来に繋がるサービスを作りたい
- 支援総額
- 0円
- 支援者
- 0人
- 終了日
- 2/20

被災地に出来た子どもの遊び場を残す あそびーばー
- 支援総額
- 2,145,000円
- 支援者
- 218人
- 終了日
- 1/16