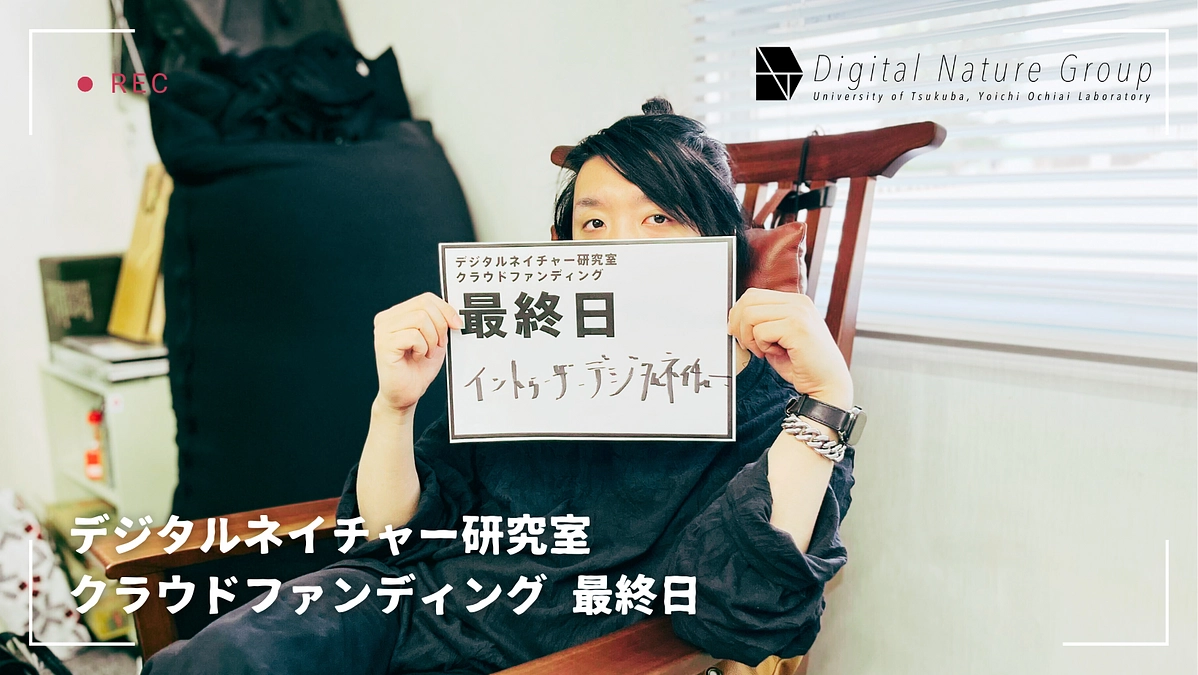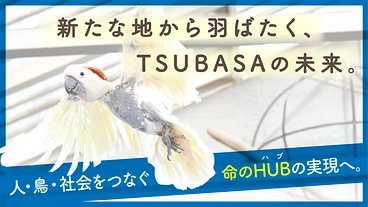寄付総額
目標金額 6,000,000円
- 寄付者
- 188人
- 募集終了日
- 2023年10月31日
【学会発表レポート】米デンバーで開催されたSIGGRAPH2024にて4件研究発表しました!

7月28日〜8月1日に米デンバーで開催された、SIGGRAPH2024に行ってきました。参加したメンバーからの学会発表レポートをお届けします!
今回の渡航経費の一部は「筑波大デジタルネイチャー研究室|研究活動支援プロジェクト」の支援金によって賄われています。みなさまのご支援により実現した発表でした、ありがとうございました。
[参加した国際学会]
The Premier Conference & Exhibition on Computer Graphics & Interactive Techniques. 2024
https://s2024.siggraph.org/
SIGGRAPH(シーグラフ)は,Special Interest Group on Computer Graphicsの略で、アメリカのコンピューター学会内でCGを扱う分科会および、同会が主催する「International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques」という国際会議&展示会の通称です。分科会自体は1967年に発足、展示会は1974年に第1回が開催され、以降、毎年1回のペースで行われてきました。
[発表したプロジェクト]
-
Dynamic Acousto-Caustics in Dual-optimized Holographic Fields
-
Floating on the Boundary: Perceptions of Reality in a Half-Digital, Half-Physical Bunny
-
Distance-adaptive unsupervised CNN model for computer-generated holography
-
EMSJUMP: Electrical Muscle Stimulation as a Wearable Training Tool for Take-off Phase of Ski Jumping
発表したプロジェクトは「筑波大デジタルネイチャー研究室|研究活動支援プロジェクト」の支援金によって実現しました。ご支援いただいたみなさまありがとうございました!!
以下、支援金にて実現した研究発表を遂行してきた学生からのメッセージを掲載します。
参加した学生からのメッセージ
情報学学位プログラム博士前期課程2年 横山拓巳
[発表題目]Floating on the Boundary: Perceptions of Reality in a Half-Digital, Half-Physical Bunny
修士2年の横山拓巳です.みなさまご支援本当にありがとうございました!
私は裸眼3Dディスプレイと現実の物体を組み合わせることで,現実とデジタルの世界に跨って存在しているような錯覚を覚える視覚体験について発表してきました.
画像のうさぎは,上半身が3Dプリンターで出来た現実のフィギュア,下半身が3Dディスプレイに表示されたCGになっています.このような表示手法について,様々な条件で体験してもらったユーザースタディの結果や知見を紹介しています.
また,本研究はArt Paperというコンピューターグラフィックスと芸術やデザインに関連した分野の研究であり,人がデジタルコンテンツに感じるリアリティについて,文化的な観点からも考察しています.
初めての学会発表で緊張もしましたが,多様な国の研究者・アーティストと自分の研究や興味,試していることなどについてディスカッション出来たことは非常に有意義で,学会を通して楽しい時間を過ごすことができました.
沢山の研究結果をシャワーのように浴び続ける日々はワクワクするもので,気になった研究発表から自分ならどのような研究に活かせるのか,つい考えてしまいます.
SIGGRAPHはアート作品のギャラリーやゲーム・アニメーション技術についての発表なども多く,多様な刺激を受けられるのも魅力の一つです.
みなさまのご支援のおかげで非常に貴重な時間を過ごすことが出来ました.ありがとうございます.
これからも面白い体験を創っていけるよう邁進していきます!!
情報学学位プログラム博士前期課程2年 筒井彩華
[発表題目]Dynamic Acousto-Caustics in Dual-optimized Holographic Fields
こんにちは!
デジタルネイチャー研究室 修士2年の筒井彩華です。
今年もSIGGRAPHという学会に参加してきました。今年はアメリカのデンバーで開催されました。デンバーは標高1,609メートルにあるとされ、Mile High Cityと呼ばれているそうです。8月だったので、過ごしやすい気候でした。
私は今回「Dynamic Acousto-Caustics in Dual-optimized Holographic Fields」というプロジェクトの共著者として、永倉くんと共に研究の発表とデモンストレーションを行いました。
研究については永倉くんが下記で説明してくれていますので、詳細はよろしければ論文やYoutubeをご覧ください。
今年は「Emerging Technologies」というカテゴリーに参加しました。
少しだけEmerging Technologiesについて説明させていただきます。
SIGGRAPHとは、CGとインタラクティブ技術におけるトップカンファレンスのことです。
「ACM SIGGRAPH は、コンピュータ グラフィックスとインタラクティブ技術に関する世界有数のカンファレンスです。何万人ものコンピュータ グラフィックスの専門家が参加する SIGGRAPH と SIGGRAPH Asia は、新しいコンピュータ グラフィックス技術と研究を発表する非常に評価の高い学会です。」
(参考:https://www.siggraph.org/)
その中のEmerging Technologiesというカテゴリーは、「グラフィックスとインタラクションの最先端の開発に焦点を当てたデモンストレーションが展示されている」ため、学会の中でも非常に賑わっているカテゴリーだと思います。学会が開催された5日間は、多くの来場者がデモンストレーションを見にきてくれます。
(参考:https://s2024.siggraph.org/program/emerging-technologies/)
私たちのデモンストレーションは点光源を使用してcausticsを投影していた関係で、会場を暗くしていたため、この写真が唯一明るく写っている写真でした。笑
Emerging Technologiesでしか体験できない面白いデモンストレーションもたくさんありました。
触覚フィードバックを床に適応したデモンストレーション。私自身アクセシビリティの研究も行っているので、この技術を用いた将来的なアプリケーションについて議論することが出来ました。
SIGGRAPHには研究者だけではなく、アーティストの方も参加されるので、今後の研究の展開について、研究者とアーティスト視点からアドバイスをいただくことができ、私自身とても勉強になりました。またSIGGRAPHに参加すると、来年も参加できるように頑張ろうという気持ちになれます。
皆様のご支援のおかげでSIGGRAPHに参加し、最新の研究に触れることができました。実際に学会に参加することで、世界中の研究者と最新の研究や技術について議論することができるので、私自身の視野も広がりました。来年は博士課程に進学する予定なので、今年のSIGGRAPHでの経験を活かして、今後も社会に貢献できる研究を行っていきたいと思います。
この度はご支援いただき誠にありがとうございました。
情報学学位プログラム博士前期課程1年 浅野悠人
[発表題目]Distance-Adaptive Unsupervised CNN Model for ComputerGenerated Holography
M1の浅野 悠人です。皆さんは計算機合成ホログラム (CGH) ご存知でしょうか。
CGHは特殊な縞模様で、レーザーを当てると空中に3次元の像を再生します。この像は完全な立体視が可能で、将来的には究極の3Dディスプレイになるとも言われています。
ところが、この原理を活用してある像を表示しようと思った時に、完璧に映すことのできるホログラム(CGH)を求める方法は見つかっていません。近年では畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて高速・高精度にホログラムを合成する研究が登場してきたのですが、汎用性に難点がありました。そこで、一部分において汎用性を向上させる研究を行いました。
私の発表形式は「ポスター」で、SIGGRAPHの中では一番簡単にチャレンジができるカテゴリーとなっていました。
会場全体にポスターがずらっと並び、参加者たちがポスターのタイトルや図をみながら、興味があったら話しかけてくれるという形です。話を聞いてくれた方から有益なアドバイスをいくつも頂くことができ、この研究をちゃんと論文にまで持っていこうというモチベーションが向上しました。初めて学会に参加することができて、とても楽しかったです!
情報学学位プログラム博士前期課程1年 中村翔音
[発表題目]EMSJUMP: Electrical Muscle Stimulation as a Wearable Training Tool for Take-off Phase of Ski Jumping
修士1年の中村翔音です。ご支援ありがとうございました!初海外&初国際学会だったため、学ぶことが多い一週間を過ごすことができました。
私は、スキージャンプの踏み切り動作のトレーニングツールとして、電気筋肉刺激(EMS)がジャンプの動作や感覚にどのような影響を与えるかを探求しました。簡単に言うと、EMSは筋肉に電流を流して筋収縮を誘導する方法なので身体が勝手に動きます。ジャンプ中に流すと高く飛んだような感じがしたり、関節の伸展速度に影響を与えます。
SIGGRAPHはCGの研究が多いですが、私の研究はInteractive Techniquesという人とコンピュータの間で相互作用を可能にする手法や技術に当てはまります。
英会話も得意というほど得意ではないし、ポスターを見に来る人もCG系の人であったりするため、ポスター発表をするときはかなり体力を使いました。しかし、国際的な場で議論したり、研究を発表し、知ってもらうことができたのでとても貴重な経験となりました。
ちなみにコロラド州はスキージャンプに縁がある場所で、古くからスキージャンプが行われていたそうです。(コロラド歴史館)
最後に、面白かった研究・作品をいくつか紹介したいと思います。
とても驚いたのが、企業ブースの3Dモデルの生成系AI。ポリゴン数が調整可能で数分で生成されてしまう。現実に存在するような車とか、椅子とかはもちろんですが、バイクに乗るトカゲのような謎なプロンプトでも破綻せずに生成されていました。しかし、人の顔は人の顔をしていなかったのでまだこれからだなという感じでした。
また、Emerging TechnologyではSkill picker という、ピンセットの握る力を可視化し、熟練者と自分のピンセットの使い方の差分が分かり、近づけていくことで上達を促すデバイスがありました。この技術が自分の研究と共通している点は、外部から見えにくい技能、特に身体感覚や運動感覚にアプローチし、学習者が自身の身体的感覚や運動を洗練させるプロセスを支援するところです。そういった、曖昧で、言語化しにくい感覚や身体知を取り扱い、何を実装すれば役に立つのだろうかという分野にまだまだ課題を多く感じました。これからも頑張っていこうと思います。ありがとうございました!
情報学学位プログラム博士前期課程1年 永倉昂暉
[発表題目]Dynamic Acousto-Caustics in Dual-optimized Holographic Fields
修士一年の永倉昂暉です。今回、SIGGRAPH2024で「Dynamic Acousto-Caustics in Dual-optimized Holographic Fields」というプロジェクトを発表しました。この研究は、超音波を利用して液体表面を制御し、複雑かつ美しい光の屈折パターン(コースティクス)をリアルタイムに生成することを目指しています。これらのコースティクスは、光が水やガラスのような透明体を通過するときに発生する、光の焦点やパターンを指します。私たちの研究では、これを動的に制御するために、デュアル最適化ホログラフィックフィールドを使用しています。
Emerging Technologiesは、最新技術や革新的なプロトタイプを紹介する場であり、研究者や企業の方々が直接体験しながら意見交換を行うことができます。多くの参加者が私のブースに訪れ、自分の研究に対して具体的なフィードバックをいただくことができました。特に、海外の研究者からの視点は非常に新鮮で、自分の研究の改善点や新しいアプローチを学ぶ良い機会となりました。
「Emerging Technologies」では、5日間にわたってデモ展示を行います。ずっと英語で説明です。とても大変でしたが、手伝ってくれた仲間のおかげでなんとかやり遂げることができました。
会期中は常に自分のブースにいる必要があったので、なかなか他の発表などを聞きに行くことは難しかったのですが、それでも手伝ってもらっている間に、「Emerging Technologies」エリアの他の展示デモを見て回ることが出来ました。ちなみにこのセクションは例年、他のセクションに比べても特に日本人が多いセクションです。
かつて落合先生と共に「Fairy Lights in Femtoseconds」を開発した熊谷先生率いる宇都宮大学のチームもEmerging Technologiesセクションにて、インタラクティブな体積映像を描画できるボリュメトリックディスプレイシステムの展示を行っていました。画像はこのシステムで僕が描いてみたドラえもんです。見えませんか?見えますよね?ドラえもんに。
現地では、多様な技術やアイデアに触れることで、新たなインスピレーションを得ることができました。初めての国際学会参加で緊張もありましたが、多くの貴重な経験を積むことができ、本当に充実した時間を過ごすことができました。皆様のご支援に心から感謝しています。今後も、より一層研究に励み、さらに多くの人に役立つ技術を開発していきたいと思います。ありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[NEWS] DNG in SIGGRAPH 2024 / 米 デンバーで開催されるSIGGRAPH 2024にて発表を行います
支援金にて実現した研究発表に関して、今後も実施報告として投稿していく予定です。
次回以降の投稿もぜひご覧いただけると嬉しいです!
これからも研究活動を精力的に行なっていきます。
応援よろしくお願いいたします!
全ての研究プロジェクトはこちらからご覧いただけます。
デジタルネイチャー研究室Webサイト
ギフト
5,000円+システム利用料

サンクスメール
●サンクスメール
●寄附金受領証明書
●公式ホームページにお名前掲載(希望制)
- 申込数
- 65
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年2月
10,000円+システム利用料

オンラインワークショップ(1種類)
落合陽一によるワークショップです。音(MusicGen等) or 映像(Stable Diffusion等) or 文章(ChatGPT等) から1種類お選びいただけます。
ーーーーーーーーーーー
●オンラインワークショップ(1種類)
●サンクスメール
●寄附金受領証明書
●公式ホームページにお名前掲載(希望制)
●学会発表の報告書(PDF)
※オンラインワークショップ:ライブ配信で実施し、アーカイブ配信も行います。2024年1月中旬〜2024年6月末までの間で1回の実施を予定しております。詳細は2023年12月末までにご連絡いたします。
- 申込数
- 65
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月
5,000円+システム利用料

サンクスメール
●サンクスメール
●寄附金受領証明書
●公式ホームページにお名前掲載(希望制)
- 申込数
- 65
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年2月
10,000円+システム利用料

オンラインワークショップ(1種類)
落合陽一によるワークショップです。音(MusicGen等) or 映像(Stable Diffusion等) or 文章(ChatGPT等) から1種類お選びいただけます。
ーーーーーーーーーーー
●オンラインワークショップ(1種類)
●サンクスメール
●寄附金受領証明書
●公式ホームページにお名前掲載(希望制)
●学会発表の報告書(PDF)
※オンラインワークショップ:ライブ配信で実施し、アーカイブ配信も行います。2024年1月中旬〜2024年6月末までの間で1回の実施を予定しております。詳細は2023年12月末までにご連絡いたします。
- 申込数
- 65
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
- 現在
- 216,672,000円
- 支援者
- 12,279人
- 残り
- 30日

義足ユーザーの「走りたい」を叶えたい サポーター募集
- 総計
- 28人

低賃金の新人アニメーターに住居支援し、割の良い仕事を作りたい!
- 総計
- 39人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい
- 総計
- 162人

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025
#子ども・教育
- 現在
- 6,769,000円
- 支援者
- 538人
- 残り
- 26日

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦
- 現在
- 5,604,000円
- 支援者
- 344人
- 残り
- 37日
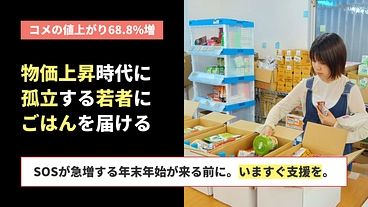
物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬
- 現在
- 11,484,000円
- 寄付者
- 306人
- 残り
- 30日

全国常連校を目指して!長崎日大高校サッカー部環境改善プロジェクト
- 支援総額
- 4,691,000円
- 支援者
- 159人
- 終了日
- 5/31
福岡天神にアマチュアスポーツライブ配信カフェをオープンします!
- 支援総額
- 1,000,000円
- 支援者
- 31人
- 終了日
- 9/30
ケニアで健康的な身体づくりのための食品を開発しテスト販売をしたい
- 支援総額
- 73,000円
- 支援者
- 8人
- 終了日
- 8/21
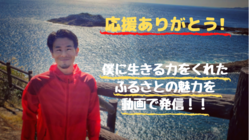
精神科の閉鎖病棟から生還した僕がオートバイで宮崎をPRしたい!
- 支援総額
- 600,000円
- 支援者
- 30人
- 終了日
- 2/28

瀬戸内・男木島の古民家から地方創生。里山を守る循環型ホテルをつくる
- 支援総額
- 3,410,000円
- 支援者
- 206人
- 終了日
- 11/8

小豆島大観音|小豆島の象徴・心の拠り所を、100年先も守りたい。
- 支援総額
- 5,229,000円
- 支援者
- 54人
- 終了日
- 11/29

山形城最後の藩山形水野藩首席家老、水野三郎右衛門元宣の銅像再建へ。
- 支援総額
- 4,930,000円
- 支援者
- 129人
- 終了日
- 7/9