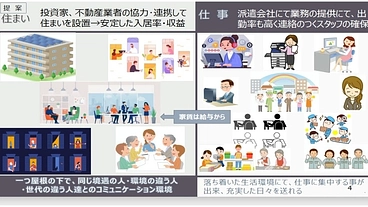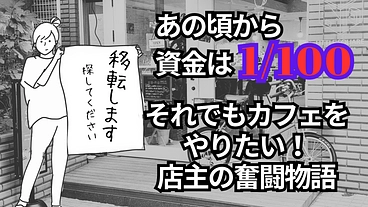寄付総額
目標金額 1,500,000円
- 寄付者
- 127人
- 募集終了日
- 2020年6月12日
畑中良輔《「天の夕顔」による四つの歌》
学友たちの作品②
学友たちの作品、2回目は畑中良輔さんをご紹介します。畑中さんは声楽専攻でしたが、橋本國彦先生に作曲も師事しました。後年は声楽家、教育者あるいは音楽評論家としての顔が目立つようになりましたが、学生時代から歌曲を中心に多くの作品を作曲しています。

◆畑中良輔(1922~2012)プロフィール
畑中良輔さんは大正11(1922)年2月12日、福岡県門司市(現北九州市)に生まれました。母が箏と三味線の師匠、父もアマチュアながら尺八を吹いていたこともあり、小さいころから邦楽に囲まれて育ちました。畑中さん自身も箏を弾くようになり、小学校4年の時の学芸会では、宮城道雄の童曲《うさぎ》などを披露しています。
小学校時代は勉強が苦手で、特に算数が不得手だったとご本人が告白していますが、その代わり、家にあった「日本文学全集」を片っ端から読んでしまう文学少年だったようです。この文学好きは、後に東京音楽学校でも発揮され、風巻景次郎先生の古典文学の講義を通しての日本語への理解が、歌を勉強する過程でおおいに役立ったと言っています。
勉強が苦手な畑中さんでしたが、受験勉強の末、県立門司中学に合格します。そして喇叭鼓隊というサークルに入り、小太鼓を始めますが、これもまた音楽学校入学後に役に立ちました。中学卒業後、ピアノや歌の基礎を懸命に勉強し、昭和15年、1年間の浪人生活を経て、めでたく東京音楽学校への入学を果たします。
そして声楽を澤崎定之先生、のちにヘルマン・ヴーハープフェニヒ先生に師事、作曲と対位法を橋本國彦先生のクラスで学びました。同期の声楽部は秋元雅一朗さん、戸田敏子さんら12名で、ピアノ科の中田喜直さんを含む4人の仲間と仲良くなったことは、前回中田さんの「新着情報」で書いたとおりです。
畑中さんの自伝的著書『音楽青年誕生物語』(音楽之友社)には、学生時代の生き生きとした生活が描かれています。それによると、在学中は問題児だったらしく、学校から2度にわたって始末書を書かされ、教官から「3回目は退学だ」と脅かされたこともあったようです。
その2度目の始末書を書かされる原因となったのは、畑中さんが本科2年の時にプロデュースした「新しい日本歌曲の創造」というコンサートでした。創作歌曲に強い関心を持っていた畑中さんは、同学年や下級生の作曲学生の新作歌曲を発表する演奏会を企画します。そこでは村野弘二、團伊玖磨、大中恩といった下級生、同級生の草川宏、中田喜直らの新作が披露されました。しかし学校に「集会届」を提出していなかったため、教官の呼び出しを食い、説教されたあげくに始末書まで書かされたのでした。そのために村野さんのオペラ《白狐》のアリアを聴き損ねたことが残念だったと、著書に綴っています。
昭和18年9月、本科声楽部を繰上げ卒業。翌19年召集され、姫路の陸軍中部54部隊に配属されます。昭和20年には陸軍一等兵として北支、中支と転戦し、終戦は上海で迎えました。捕虜となり1年間使役人として使われた後、昭和21年4月に佐世保に復員します。学校へ行ったところ、知らないうちに研究科を卒業したことになっていたのを知り、聴講科に籍を置き、ブランクを取りもどすために、ヴーハープフェニヒ先生のレッスンを再開しています。

その後、畑中さんは作曲家グループ「新声会」に参加し、演奏と作曲の両面で活動を開始します。昭和22年9月には、中田喜直さんのピアノ伴奏で、「畑中良輔第1回独唱会」を開催。また翌23年12月には、藤原歌劇団公演のモーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》でオペラ歌手としてデビューします。
教育者としては、昭和24年、東京音楽学校と東京美術学校が統合されて東京藝術大学が創設されると講師に就任。以来昭和58年まで35年の長きに渡って母校の教授として後進の指導に当たりました。合唱の分野でも、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団を50年以上に渡って指導するなど、音楽愛好家の裾野を広げる活動にも尽力しました。このように日本の音楽界に大きな貢献をした畑中さんでしたが、平成24(2012)年5月24日、間質性肺炎のため90歳で亡くなりました。
◆《「天の夕顔」による四つの歌》について
昭和18年3月、畑中さんが本科3年の時に作曲した最初の歌曲集です。『天の夕顔』は、昭和12年『日本評論』に発表された新感覚派の小説家・歌人の中河與一(1897~1994)の代表作です。人妻に恋した主人公のプラトニックな純愛を描いた小説で、40万部のベストセラーになりました。この小説に共感した畑中さんは、主人公の生き方について、友人の女子生徒と論争を繰り広げたこともあったようです。
タイトルは《「天の夕顔」による四つの歌》ですが、実際のテキストはこの小説から取られているわけではなく、同じ作者の歌集『秘帖』から、畑中さんが小説のテーマを表現していると考えた4つの短歌を選んで作曲したものです。選ばれた短歌は次の4首です。
Ⅰ まがなしき ひと眼を欲りて はるばると 山川の旅 超えゆきにけり
Ⅱ いつの日か また逢ふべしと 思ふにも 今日の別れの 死にて思ほゆ
Ⅲ いづくにか 君を求めむ 遠空の はてと思ふは かなしかりけり
Ⅳ 山にゆき 野にゆき思ひ たへぬ時 泣きて見らるる み空なりけり
当時師事していた橋本國彦先生からは激賞されたそうですが、畑中さん自身は自作解説で「未熟、若書きではあるが、その時の純情一途な想いは、後年の作品よりもより切迫した「念い」が噴出しているように思う」と述べています(全音楽譜出版社『畑中良輔歌曲集(増補改訂版)』より)。
昭和17年8月、東京音楽学校の学生たちは「満州国建国10周年祝賀音楽使節」として満州を訪れました。その一員であった畑中さんは、たまたま『天の夕顔』の作者中河さんと、大連へ向かう船で乗り合わせ、早速彼の船室を訪れて知己を得ました。それが縁となり、この《「天の夕顔」による四つの歌》の私的な初演は、成城の中河さんの自宅で行われました。そして公的な初演は昭和21年10月、NHKラジオの「現代日本の音楽」の放送でした。(大石泰)

参考文献:畑中良輔『音楽青年誕生物語』(音楽之友社)
『畑中良輔歌曲集(増補改訂版)』(全音楽譜出版社)
ギフト
3,000円

「戦没学生のメッセージ」プロジェクト応援コース
お礼状、クリアファイル
- 申込数
- 34
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年6月
10,000円

「里帰りコンサートin旧奏楽堂」応援コース①(コンサート不参加)
お礼状、クリアファイル
コンサートプログラムにお名前記載(希望者のみ)
当日のコンサートプログラム
- 申込数
- 20
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年8月
3,000円

「戦没学生のメッセージ」プロジェクト応援コース
お礼状、クリアファイル
- 申込数
- 34
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年6月
10,000円

「里帰りコンサートin旧奏楽堂」応援コース①(コンサート不参加)
お礼状、クリアファイル
コンサートプログラムにお名前記載(希望者のみ)
当日のコンサートプログラム
- 申込数
- 20
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年8月

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい
- 現在
- 3,581,000円
- 支援者
- 125人
- 残り
- 21日

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター
- 総計
- 275人

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を
- 現在
- 4,944,000円
- 寄付者
- 207人
- 残り
- 71日

アレッシ・バウスフィールド・リンドバーグ×東京佼成WO夢の響宴へ!
- 現在
- 4,225,000円
- 支援者
- 108人
- 残り
- 39日

「科学の芽」賞と子どもたちの「好き」を一緒に応援しませんか?
- 現在
- 1,950,000円
- 寄付者
- 96人
- 残り
- 9日

ジュエリー作品が国境を越える | 学生13名、海外への挑戦
- 現在
- 395,000円
- 支援者
- 45人
- 残り
- 18日

全国の学生に、世界に通用するビジネス・英語コミュニケーション能力を
- 現在
- 114,000円
- 寄付者
- 10人
- 残り
- 21日